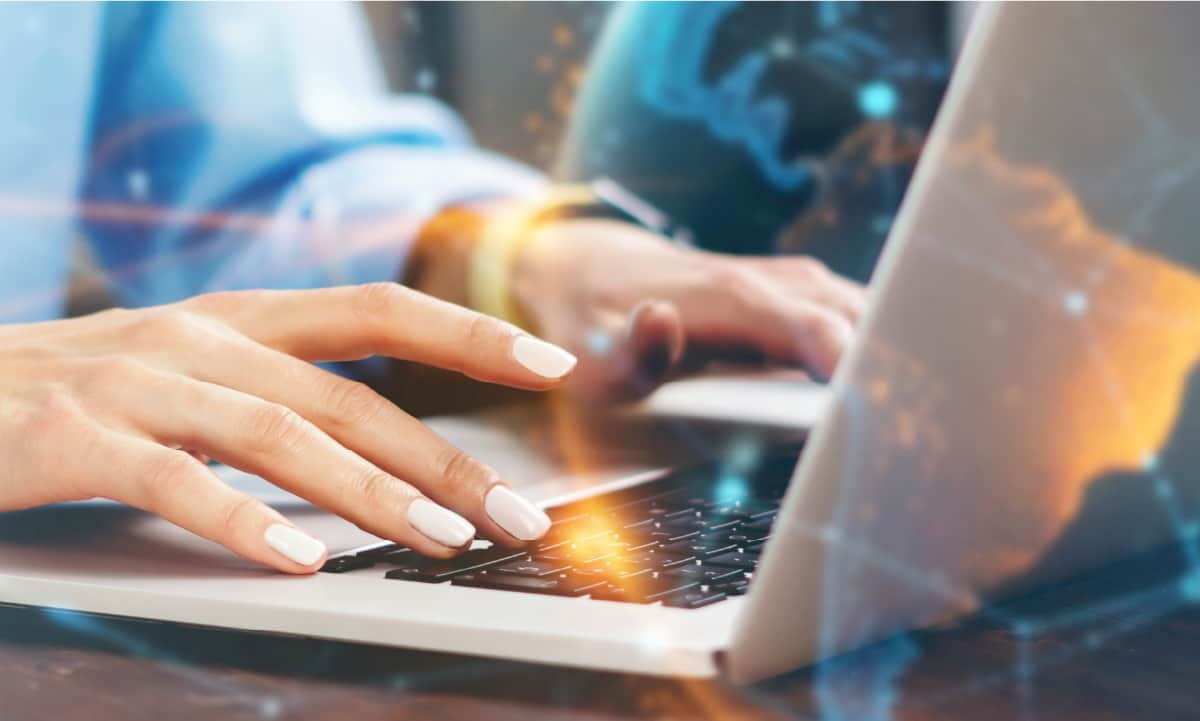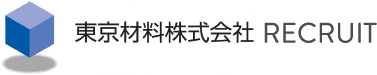誰でもわかる!合成ゴム
東京材料では、幅広い産業分野に合成ゴムとその配合剤を届けております。ここでは、ゴムそのものの特性や、日常でどのように使われているか?そしてゴム営業に携わることの魅力について、多角的にご紹介していきます。
ゴムって、どんな特徴があるの?
輪ゴムなど、日常でなんとなく使ったり、目にしたりするゴム。実はさまざまな製品の目に見えにくい部分で活躍しています。実際に東京材料で取り扱うゴムの多くは、自動車部品メーカー向けに供給されています。ゴムとは、弾性を持つ高分子化合物。その特徴は、小さな力でも変形し、すぐに元に戻る性質を持つこと。そんな強みを核にしながら、ゴムの豊富な用途をお伝えします。

こんなところに、ゴム!
水、オイル漏れを防ぐシーリング。
水筒の蓋を外すと見えてくる、パッキン。それは、黒くて細いゴムの輪です。これに象徴されるように、多彩な液体やガスなどの漏れを防ぐことができるのもゴムの特性。工業用では、さまざまな機器のオイル漏れを防ぐシーリングにも使われています。また、同じ特性を活かしたガソリンスタンドなどでガソリンを入れる際に使うホースなどにも使われています。

握力が買われています。
ゴムには対象物に対してグリップする力=止める力もあります。そんな握力に着目して、見出された用途が、プリンターに使われるロール。まさにゴムの掴む力を使って、紙送りなど搬送する箇所に何点も使われています。もちろん、シンプルに紙を送るだけのロールもあれば、さらに機能性を持たせた特殊なゴムのボールなども。お客様であるメーカーが、ゴムにいろいろな特性を持たせて市場に出しています。

足元で安全を支える、ゴム。
スニーカーや、学校の校舎内で履く室内履きや体育館シューズなどの靴底に。滑りにくいグリップ力を活かした、ゴムが選ばれています。しかし、工場で働く人々の足元を支える安全靴の靴底の場合は少し特殊です。安全靴にとって、滑りにくさはもちろんですが、最も大切なことは静電気を起こさないこと。靴底が地面などに触れた際に起こる静電気の火花により、大規模な工場火災につながることもあるのです。そのため、耐電性という機能を持たせた合成ゴムが使われています。

車のタイヤはなぜ黒い?
ゴム製品といえば自動車タイヤ。黒のイメージが一般的ですが、実はゴム本来の色は、透明に近い白や黄色。実際に、自動車が発明された頃はゴムの樹液そのものの色をしたタイヤもあったそう。しかし、強度を増すためにカーボンブラックと呼ばれる黒い炭素の粒を混ぜるようになりました。他にも汚れが目立たないなどの利点も。このカーボンブラックは黒色の着色材として、印刷インキやトナーにも使われるもの。タイヤは赤や青でも作れますが、今のところ黒の一人勝ちです。
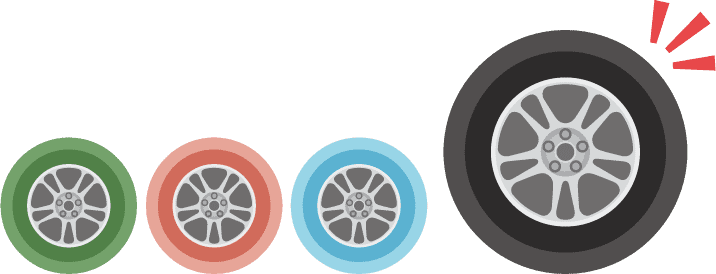
ゴムビジネスの最前線
ゴムを巡る業界の特徴はなんといっても安定性。タイヤに使われたゴムには130年の歴史があるように、一度、使用されたら永くしっかりとビジネスが継続されるのが事業の大きな魅力です。そうした安定したビジネスの延長上に、新たな市場の可能性も広がっています。
150℃から-40℃に耐える、原料を探して。
走行中は90℃前後まで温度が上がる、自動車のエンジンオイル。エンジンやモーターに使われるオイルシールは絶えず加熱と冷却を繰り返し、さらに熱帯地域や寒冷地など、どのような場所でもオイル漏れを防ぐ高い耐久性が求められます。近年は、省エネ性能を高めるために「-40℃に耐えるエンジン用のオイルシールを作りたい」などの広い温度領域ニーズも増え、国内外のネットワークを活かして理想に叶う材料を探すことも。また、水素燃料電池を利用した自動車など、EV車のさらに進んだNEV車向けに適応したオイルシールを作るための材料の開発支援など、新たな市場の開拓にも力を入れています。

ゴムの営業は、関係づくり。
歴史があり、息が長い商材であるゴムの営業は、じっくりと時間をかけて関係を作っていくことが大切。お客様が数年に一度の材料を見直す機会に声を掛けて頂けるかは、営業の日頃の努力の成果でもあるのです。そんな営業が「嬉しい」と達成感を得るのは、お客様がお困りの時に声をかけてくれたとき。そんなお困りごとで多いのは、必要な材料が届かない時など。製造ラインを止めるわけにいかないとお客様がお困りの際には、自社のネットワークを生かして必要な材料を確保したりと、危機を救ったエピソードに事欠きません。そんなゴムの営業は、国内外問わず、さまざまな人たちと良い関係を作れる、そんな人が多く活躍しているのです。

机の上で、世界を股にかける事務!?
東京材料で取り扱うゴム製品において、お客様からの受注以降すべての手配を行うのが事務。国内のオーダー対応のみならず、材料の輸出入にも携わります。時にはお客様のニーズに合わせて、工場の近くに倉庫を探したり、倉庫での在庫管理なども行います。輸入を行う際に気をつけるのは、近隣のアジアの国々と、遠方のヨーロッパなどとの対応の違い。日本から離れたドイツなどでは、一回に20トンなどのコンテナ単位で手配します。さらにその手配は半年ほど前から。半年前に注文を確定し、海外メーカーに製造を依頼します。また、その後は、船便の手配や到着時期に国内の倉庫に連絡し、損害保険をかける。モノが届けば輸入通関や関税処理をする。そして、税関を抜けたら倉庫へ。そして納入予定の倉庫とは、国内でも、横浜、神戸、大阪など全国各地に。このようにデスクの上で、世界中を動かすのが事務の仕事なのです。